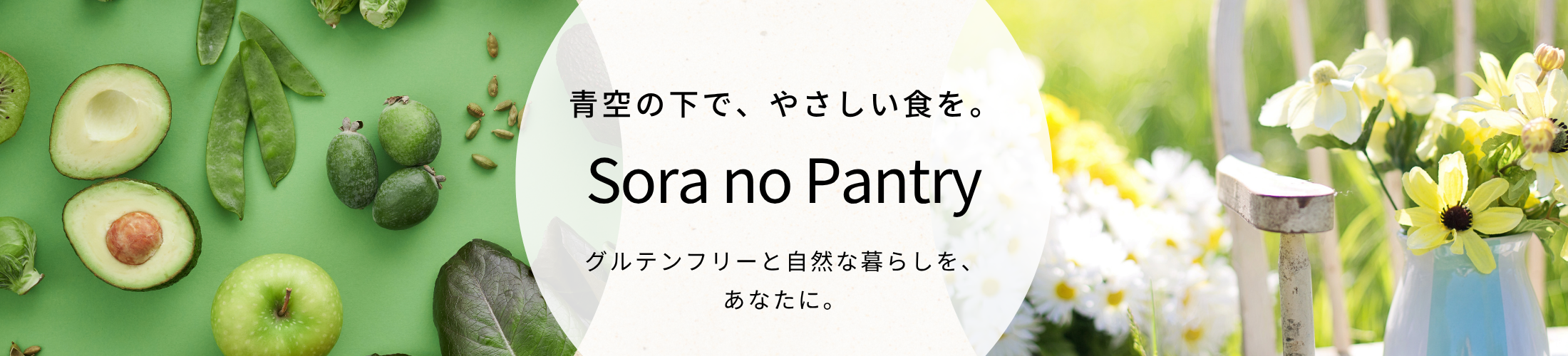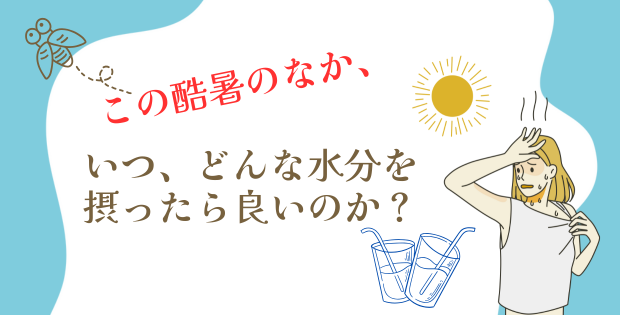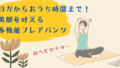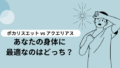※本記事にはプロモーションが含まれています。
2025年は40°を超す日があり、水分補給の大切さをひしひしと感じます。ただ、一方で水分過多は胃液の分泌や消化に影響を与える可能性があると言われています。
私は、基本的に在宅していることもあり、結構水分量は多め。飲んではトイレに行くことを繰り返しています。自分はどれくらいの水分を補給したらいいのか、以前から気になっていました。吉野敏明氏のYouTube動画が参考になったので、このページでまとめました。
Contents
猛暑の過ごし方
1.猛暑の中での熱中症による死亡者がいるため、不要不急の外出は避ける。

確かに誰かと会うといっても、夕方からとか涼しい季節になってからとか、わざわざ暑い時間に外出する必要は感じません。不要不急の外出は避けるという習慣は感染症の流行時に定着したと思います。
2.熱中症の原因の一つは、植物性の油の過剰摂取による、体温調節中枢の機能不全なので油に注意する。暑いからといって、レバニラや餃子、唐揚げといった植物油を多く含む料理、ホイップクリームやアイスクリームなどを避けるようにする。

吉野敏明氏は小麦粉・砂糖・乳製品・油の「四毒を避ける」という考え方を提唱していて、油もそのひとつです。私はサラダ油はもう何年も使用していませんが、外食では何を使っているかわからないので、気を付けようと思いました。
四毒抜きのすすめ 小麦・植物油・乳製品・甘いものが体を壊す [ 吉野敏明 ]
3.水分を取りすぎると胃液が薄まり、消化不良や夏バテにつながるため、不用意な大量摂取は避ける。カフェインを含むアイスコーヒーは利尿作用があるため、暑い時期には適さない。

水分補給の基本原則
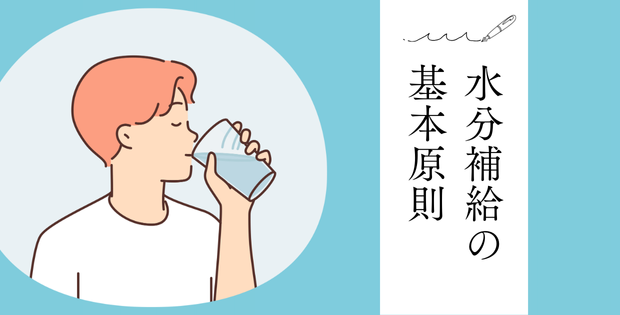
- 起床直後、就寝前にコップ1杯150-200㏄の常温水を飲む。
- 屋外での作業中は15分ごとに50-100ccの水を少量ずつ飲む。
- 帰宅したらコップ1杯1杯150-200㏄の水を飲む。
- 食事の30分以上前に水を飲む 。
- 食事中に大量の水分を摂るのは避ける。

朝は、冷蔵庫保存の水を飲みたいのですが、やはり常温水なんですね。食事中の水分は胃液が薄まると聞いたので、20代の頃から避けるのは習慣となっています。
熱中症への対処法
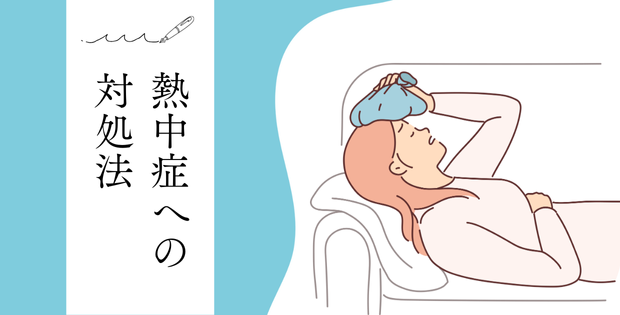
- 軽度(めまい、立ちくらみ):ポカリスエットなどを口腔粘膜からゆっくりと吸収させるように飲む。
- 中等度(頭痛、吐き気):すぐに救急車を呼び、脇の下や首などを冷やす。意識がある場合は、少量ずつ電解質飲料を飲む。
- 重度(意識障害):直ちに救急車を呼び、水を飲ませてはならない。高齢者や子供の熱中症対策について、特に注意深く見守る必要があると述べています。

日常ではポカリスエットは飲まないようにしていますが、熱中症のときは飲んだほうが良いんですね。重度のときは水は飲ませてはいけないというのは、誤嚥してしまうから。ご年配の方はそこから肺炎になってしまう場合が多いから注意が必要ですね。
最適な飲料水

それでは、どんな飲み物が推奨されるのでしょうか?吉野氏は以下の飲料を推奨しています。
麦茶
麦茶は古くから日本の家庭で親しまれてきた飲み物ですが、その健康効果は科学的にも裏付けられています。ミネラルが豊富で体温を下げる作用があるため、水分補給に最適だと推奨しています。
1. ノンカフェインであることが最大の利点
コーヒーや緑茶、紅茶に含まれるカフェインには利尿作用があります。これにより、飲んだ水分が尿として体の外へ排出されやすくなり、十分な水分補給になりにくいことがあります。一方、麦茶はカフェインを含まないため、飲んだ水分が体内に留まりやすく、効率的な水分補給が可能です。小さなお子様や妊婦の方、寝る前の水分補給にも安心して飲むことができます。
2. 血液をサラサラにする「ピラジン」
麦茶の香ばしい香りの元となっているのが「ピラジン」という成分です。このピラジンには、血管を広げ、血液の流れをスムーズにする働きがあります。いわゆる「血液サラサラ効果」です。血行が促進されることで、冷え性の改善や新陳代謝の向上にもつながります。これは、水分補給と同時に体の巡りを良くするという、一石二鳥の効果と言えるでしょう。
3. リラックス効果と血圧降下作用の「GABA」
麦茶には「GABA(γ-アミノ酪酸)」というアミノ酸が含まれています。GABAには、神経の興奮を抑える働きがあり、リラックス効果やストレス軽減作用があることが知られています。また、血圧を下げる効果も期待できるため、高血圧が気になる方にも良い飲み物です。
4. 抗酸化作用を持つ「ポリフェノール」
麦茶には、お茶の成分と同様に「ポリフェノール」が含まれています。ポリフェノールは強い抗酸化作用を持つことで知られており、体内の活性酸素を除去し、老化や病気の原因となる細胞の酸化を防ぐ効果が期待できます。

◎小麦はNGなのに、麦茶はいいの?→むぎ茶はグルテンフリー
グルテンは、小麦やライ麦に含まれるタンパク質の一種で、水を加えてこねることで粘り気や弾力性が生まれます。麦茶の原料は「大麦」ですが、以下の理由から、麦茶はグルテンフリーに分類されます。
・大麦にグルテンは含まれない
大麦にもタンパク質は含まれますが、小麦のグルテンとは組成が異なり、グルテンを形成する性質がほとんどありません。このため、大麦を原料とする麦茶は、グルテンを気にせずに飲むことができます。
・製造過程でさらに分解される
麦茶は、大麦を高温でしっかりと焙煎(熱を加える)し、その後、水やお湯で煮出して作られます。この過程で、もしごく微量のグルテンが含まれていたとしても、熱によってタンパク質が変性・分解されるため、最終的に飲料として抽出されることはほぼありません。

子供の頃はむぎ茶一択という感じでしたが、理にかなっていたのですね。久々に飲んだら懐かしさを感じました。基本的には煮出したほうが良いようです。外出用にペットボトルを用意しておくのも良さそうですね。むぎ茶はグルテンフリーということで安心しました。
炭酸水+レモン
疲労回復やデトックス、体質改善を促すための「体のメンテナンス飲料」。
1. 体液のpHバランスを整える
レモン果汁の「クエン酸」は、疲労の原因となる乳酸を分解するだけでなく、体液を弱アルカリ性に保つ働きがあります。吉野氏は、体がアルカリ性に傾くことで、細胞が活性化し、健康を維持できると考えています。
2. 血行を促進し、デトックスを促す
炭酸水の気泡(炭酸ガス)は血管を拡張させる効果があります。これにより血行が促進され、新陳代謝が活発になります。細胞レベルでの代謝が上がれば、体内に溜まった老廃物の排出(デトックス)がスムーズになり、体の内側から浄化されると彼は提唱しています。
3. ビタミンCによる抗酸化作用
レモンに含まれる「ビタミンC」は、強力な抗酸化作用を持ち、体の酸化(老化)を防ぎます。これは、病気のリスクを減らし、若々しさを保つための重要な要素だと考えられます。


夏は炭酸が飲みたくなるけど糖分が多い。そうだ!炭酸にレモン果汁を入れて飲めばいいじゃん!とよく飲んでいました。そんなこともあり、吉野氏が推奨されているので驚きました。テルヴィスのレモン果汁はお手頃なので購入することが多いです。
まとめ
麦茶:日常的に穏やかに体を整え、血液をサラサラに保つための「基本の健康飲料」。
炭酸水+レモン果汁:疲労回復やデトックス、体質改善を促すための「体のメンテナンス飲料」。
それぞれが異なるアプローチで健康をサポートするため、体調やシーンに合わせて使い分けることが「病気にならない体づくり」に繋がる、理にかなった習慣だと言えますね。